●ヤーコブソン側の事情:
ヤーコブソン先生がここでそもそもやろうとしたことはといえば[邦訳p.157]:
| 参加者が含まれる | 参加者が含まれない | |||
|---|---|---|---|---|
| designator | connector | designator | connector | |
| qualifier | gender | status | ||
| quantifier | number | aspect | ||
| voice | taxis | |||
| shifter | person | tense | ||
| non-shifter | mood | evidential | ||
これ↑を圧縮すると↓[p.158]:
| 参加者が含まれる | 参加者が含まれない | |||
|---|---|---|---|---|
| designator | connector | designator | connector | |
| shifter | Pn | PnEn | En | EnEn |
| non-shifter | Pn/Ps | PnEn/Pn | EnEs | EnEns/Es |
‥‥というカテゴリー操作でもって、これでロシア語の動詞の分類ができますよ、ということなのだった。
で、その「前置き」にて先生の曰く:人称代名詞やその他彰校劼里發墜?蓮
にあると言われてきたけれども、
[1.については:]どの転換子もそれ自身の一般的意味をもっている云々、と。これらに対置して「転換子」を特徴づけて曰く:
- たとえば I は、それが属するメッセージの発信者──you ならば受信者──を意味する。
[2については:]すべての 範疇付属語syncategorematic terms に共通していえる。
- たとえば、but という接続詞は一回毎に、述べられた二つの概念間の反対関係を示しすのであって、「反対」という一般的な観念を表すわけではない。
[「転換子」は「メッセージにreferするコード」なのだが [p.152]、] 転換子が言語コードの他のすべての構成要素から区別されるのは、ひとえに、
- それらがある与えられたメッセージに必ず関説referされなければならない
ということによってである。[p.153]
と。
そして中間的結論:
”Jim told me 'flicks' means 'movies'. 'チラチラ'って'映画'の意味だとジムがぼくに教えてくれた。”てことで、さらにここに、designator/connector 区別を導入し、「動詞範疇の分類」バナシに続いていく、と。
この短い発話は二重構造を成す四つの型をすべて含んでいる:
- 引用reported話法(M/M)[メッセージにreferするメッセージ:circularity]
- 自称的autonymous話法(M/C)[コードにreferするメッセージ:overlapping]
- 「それ自身の命名として用いられ」る。 ex.「pop は子犬という意味の名詞である」[p.151]
- 固有名(C/C)[コードにreferするコード:circularity]
- [p.151]
- 転換子(C/M)[メッセージにreferするコード:overlapping]
- 転換子の一般的意味は、メッセージにreferしなければ定義できない。
- 「象徴」は慣習規則によってそれが表示する対象に結びつけられる
- 「指標index」はそれが表示する対象と実存的な関係にある
- 「転換子」はこの両方の機能を合わせもっており、したがって、indexical symbol という類に属する*[p.152]
言語と言語の使用とにおいては、二重性は重要な役割を果たす。特に文法的範疇、なかんずく動詞範疇の分類には、転換子の体系的な区別が必要となる。[p.154]
- しかし「実存」ってのは‥‥‥(苦笑)。 言語学の本の訳語としては如何なものか。(しかしなんと訳す? 現実存在か?)
* ここで参照されているのは、バンヴェニストの著名な──「三人称代名詞は人称代名詞じゃない」という過激な(しかしある意味ごもっともな)議論を展開した──論考:
- cf. Émile Benveniste, "La nature des pronoms", (1956) in Problèmes de linguistique générale, Gallimard, (1966)
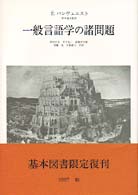 → エミール・バンヴェニスト「代名詞の性質」in
→ エミール・バンヴェニスト「代名詞の性質」in
いや〜、「妥当性」までの道のりは、まだまだ遠いですなぁ(w。
